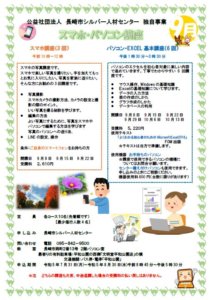佐賀県神埼 櫛田宮 ヤマタノオロチ伝説と櫛名田姫
〒842-0001 佐賀県神埼市神埼町神埼4191

櫛田宮 境内に物見櫓があり目印

北参道の鳥居
櫛田宮(くしだぐう)と読む。
ここは神社なのだが、古代から皇室と深いつながりを持っている神社なので宮という。
伊勢神宮、明治神宮、熱田神宮などと同列だ。
吉野ケ里歴史公園から15分くらいで着く。入口近くに建つ大きな物見櫓が目印になる。
入り口が複数あり、今回は北参道と呼ばれる鳥居から参拝をする。

推定700年の古木くすのき

古木くすのき
ご由緒沿革
大昔,荒ぶる神が人々を害したが,景行天皇が櫛田宮を創建されてからは厄災はなくなり神の幸の郡と名付けた(神埼郡)。今から千九百余年前 吉野ヶ里遺跡と同時代の事である。
鎌倉時代蒙古襲来の時,本宮の神剣を博多櫛田神社へ移して異賊退散を祈り,霊験あらたかなものがあったので,厄よけの神と崇敬された。

オロチ酒甕(さかがめ)
北参道の鳥居の近くには推定700年の古木くすのきがあり、その横にはオロチ酒甕(さかがめ)という岩化が祀られている。
神埼地方にはヤマタノオロチ伝説が残っており、そのオロチを酒に酔わせて退治した時の甕と云われているそうだ。古来より赤子の髪を納めて無病息災を祈る習わしがあるという。
まずこれに驚く。
オロチ伝説
これは出雲国(現在の島根県)の伝説である。
載っているのは出雲国風土記で、編纂が命じられたのは和銅6年(713年)5月、元明天皇によるが、天平5年(733年)2月30日に完成し、聖武天皇に奏上されたといわれている。「国引き神話」を始めとして出雲に伝わる神話などが記載され、記紀神話とは異なる伝承が残されている。現存する風土記の中で唯一ほぼ完本の状態である。ウィキペディア
一つの胴体に八つの頭と八つの尾をもつヤマタノオロチをスサノウが退治するという有名な伝説だ。
櫛田宮の言い伝えでは、大昔、荒ぶる神が人々を害したが、景行天皇が櫛田宮を創建されてからは厄災はなくなり神の幸の郡と名付けた(神埼郡)とある。
櫛田宮HPには更に詳しく、
大昔大蛇が住民を苦しめた。鼻は花手に尾は尾崎までおよぶ長さ六丁の大蛇。人々は野寄に集まりて協議して、柏原から柏の木を伐ってきて伏部からふすべ(クスベ)た。大蛇は苦しみ蛇貫土居をのがれ、蛇取で退治された。今も蛇取に蛇塚がある。
と載っている。
これはどういう事だろうか。
櫛田宮は、創建も古く、天皇家も深く関わっている神社である。
ただの真似ではないはずである。
この件に関しては、もう少し詳しく調べてみたい。

稲荷

稲荷

印鑰(いんにゃく)神社
境内には様々の神社が建てられている。
櫛森稲荷 櫛丸稲荷 印鑰(いんにゃく)神社など。
印鑰とは役所の印鑑と鍵のことで、当社地が神埼の中心だったことを裏付けているという事だ。

肥前鳥居

琴の楠

推定樹齢1000年 琴の楠

弁天池
神社の正面に回り、一の鳥居から参拝する。
この神社は長崎街道神埼宿だった場所。その石碑が建てられている。
入り口左手には、伝説のクスノキ「琴の楠」が植えられている。
景行天皇が埋めた琴から芽が出て、このクスノキになったという。清浄な人が息を止めたままこのクスノキを 7 回半回れば、琴の音色が聞こえるという言い伝えがある。
驚くのは推定樹齢1000年と言われている事。
今回行ってみると、この木の治療の為だろう。洞の中が真っ黒く塗られ、支木でしっかりこの木を保護していた。
その先に二の鳥居があるが、この鳥居も有名で肥前鳥居という。
肥前鳥居の特徴は、鳥居の上部構造である笠木かさぎと島木しまぎが一体化して両端部(鼻)が流線形にの伸びていることが挙げられる。また、両端の柱が下にゆくほど太くなっている。 佐賀県全域に分布している。慶長年間(1596-1615)が造立のピークであったことから「慶長鳥居」とも呼ばれる。

神門

随神

櫛田宮

櫛田宮

櫛田宮
その先の神門を抜けると本堂である。
独特のしめ縄のしめ方である。これも又なにか曰くがありそうだ。
祀られているのは櫛田三柱大神。
・櫛稲田姫命(クシナダヒメノミコト)正面御座、櫛田大明神
・須佐之男命(スサノオノミコト) 東御座、 高志大明神
・日本武命 (ヤマトタケルノミコト)西御座、 白角折大明神
元々この神社の祭神は、大正時代までは、素戔嗚尊、櫛稲田姫、手名椎命足名椎命だったのだが、日本武尊に変わったそうだ。
これはどんな理由なのか知りたいものだ。
まとめ
大切な部分を抜き出してみた。
櫛田宮は皇室領荘園「神埼荘」の総鎮守として、中央と密接な関係を持った神社だという事。
ヤマタノオロチ伝説がある事。
この神社の創建が、今から千九百余年前の吉野ヶ里遺跡と同時代だという事。
櫛田宮と南北各1里へだてて鎮座する高志(たかし)神社・白角折(おしとり)神社とは三所一体の神社だという事。
博多には博多櫛田神社があり、鎌倉時代蒙古襲来の時,本宮の神剣を博多櫛田神社へ移して、異賊退散を祈り,霊験あらたかなものがあったので,厄よけの神と崇敬されている事。
他にも興味深い伝説があり、かなりボリュームのある神宮である。
これから深く考えたいと思っている。
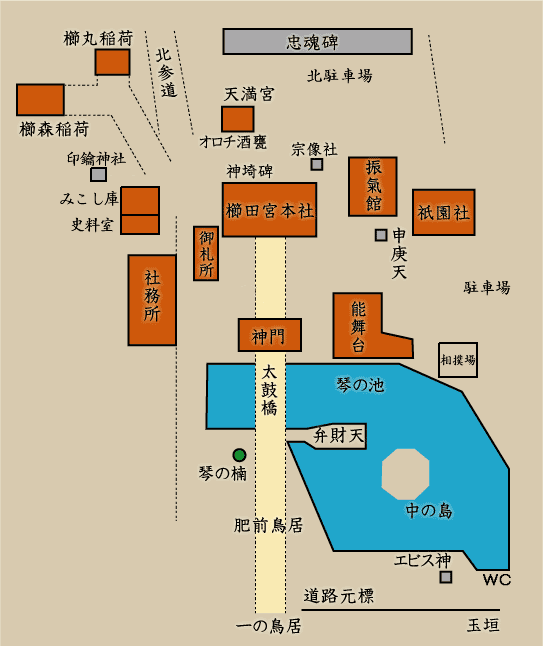
櫛田宮HP 配置図

祇園社

北参道の紫陽花