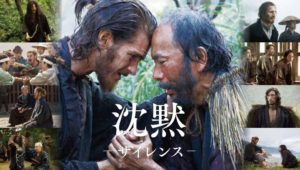水の浦 湊明神稲荷神社 水の浦天満宮 岩と水とモノレールの町
水の浦町という町がある。
対岸地区の三菱電機がある丸尾町と隣接している細長い町である。
反対側は三菱重工がある。長崎三菱信用組合がある場所だと言ったほうがわかりやすいかな。
特別書くことがない町なのだが由来はある。
水の浦の地名の由来は、この地にきれいな湧水が湧いていたからだという。
水の浦天満宮
その中で一番きれいだったのは水の浦天満宮の井戸だったという。
又その付近は大きな溜り池となっていて、この溜池の水を黒船に売っていたという言い伝えがあるという。
この地には筑前屋敷があったというから、その住人が販売していたのだろう。
(出典 稲佐風土記 松竹秀雄著)
筑前は今の福岡の太宰府あたりである。
黒船という事なので時代は江戸時代後期だったのだろう。(黒船は東京だけではなく、長崎にもロシアの船は来ていた)
古代から湧き水は出ていたはずで、水の浦は水の町だったと思われる。
水の浦天満宮は今でもある。

水の浦天満宮
町中に入っていった所にあるのだが、前に建物が立っていてわかりにくい。
超細い道を行くと鳥居と祠があり、天満宮のシンボル「石像の牛」があった。

水の浦天満宮
ちゃんと残っているのは良いことだと思う。
湊明神稲荷神社
またこの場所の近くには湊明神社(湊神社)もある。

湊明神稲荷神社
湊明神社の赤い鳥居があり、そこには正一位湊明神稲荷神社と書かれている。

湊明神稲荷神社
この名前はなんか変である。
正一位というのは神社の位で最高位の称号である。この称号は普通稲荷神社に付けられているものだ。ところが湊明神という神様の名前が入っている。
不審に思い調べてみた。
そうする水の浦町の湊明神稲荷神社は、江戸時代の初期に創設されたとある。
更に調べると、兵庫県の湊神社について載っていた。
当社は、昔「鵜湊明神」と称していました。神宮皇后の三韓征伐の時、当湊神社に船を着け、当社に参拝し、征討の吉兆を占うために、自ら弓をとり、射の技を試みたところ、吉の様子が出たので、この縁により、村名を的形といい社号を「湊」と云ったといわれています。
(郷土史 的形より)
https://sites.google.com/site/marchjudd/Home/matogata/jinja/minatojinja
また
宮城県の湊明神には海上安全と阿武隈河口の湊の守護神。悪魚を悉く平定し、常に大鮫の頭上に神座するといわれる。
http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/C0410905-000.shtml
とある。
結局よくわからないが、全国的に存在するというのだけがわかる。
兵庫県の「神宮皇后の三韓征伐」の由来だが、長崎港にも神宮皇后伝説はたくさん残っており、そのつながりかもしれない。
湊明神稲荷神社の稲荷神社の方は由来がわかる。
稲荷神社は日本中にあるポピュラーな神様だ。京都にある伏見稲荷大社が総本宮で朱い鳥居と、神使の白い狐がシンボルである。
祀っている神様は穀物・食物の神を主な祭神とする場合が多い。
全国的に広がっており、商人の神様という認識が強いのだが、何でも受け入れているようで、とくに特別な宗教的要素は弱いようである。

湊明神稲荷神社
神社は大きな岩に寄り添うように立てられている。岩にはくぼみが掘られており、お稲荷さんが祀られている。

湊明神稲荷神社

湊明神稲荷神社
足元の石碑には「宇佐八幡大神」があった。宇佐というのは大分県の宇佐神宮のことである。

湊明神稲荷神社の石碑
なぜ稲荷神社に「宇佐八幡大神」という石碑があるかというと、宇佐は稲荷神社の発祥の元だからだ。
そもそも稲荷は秦氏という渡来系の一族の氏神であったとされている。
その意味を込めて湊明神と言ったのだろうか。つまり秦氏を神格化したのが湊明神かもしれない。
そう解釈すれば「宇佐八幡大神」という石碑があるのも理解できる。
湊の意味
湊明神の湊という漢字だが、同じ意味で港という文字もある。
湊(みなと)という字は「水の門」を意味していて、古くは、港湾施設のうち水上部分を「港」、陸上部分を「湊」と呼んだとある。
由来や成り立ち
「湊」は「水が集まる」「船着き場」を意味する漢字です。この由来にはツクリにある「奏(ソウ)」が深く関係しています。
「奏」は「神様が降りてくるように、ものを差し出す様子」を表した漢字で、「物を差し出す→物が1ヶ所に集まる」と変化し、これに「水」を表す「さんずい」を組み合わせて「水が集まる場所」の意味が生まれました。
つまり湊明神は水や港の神様という意味だと思われる。
水の浦は湧き水が豊富だったということから、湊という文字を使ったのだろう。
港町ではなく水が湧き出て海の近くにあり、人が集まった場所という意味で湊という文字を使い、その守護神が湊明神だと言えるだろう。
岩の町
細長い町なので入り口は長崎三菱信用組合あたりからである。

水の浦橋
左手には水の浦橋があり、川を隔てて大谷町である。
何の変哲もない細い上り坂の路地を歩いていると、はっとする物を見つける。
それは巨大な岩石である。

水の浦町の岩
よく見れば結構ある。
この町は大きな岩石だらけの町だったのだ。

水の浦町の岩
それを人間が住めそうな場所を選んで開拓していったんだと実感する。
そういえば水の浦町入り口の右手にも巨大な岩がむき出しになっている。

水の浦町付近の岩
今は開発され埋め立てられて昔の面影はないが、稲佐山のふもとの海岸線は、切り立ったがけが多かったとある。
そう思えば、稲佐山も岩だらけである。
岩瀬道、立岩町、岩見町、岩屋山、岩川町などの町名も岩の町を表している。
それは当然長崎の地形にあり、昔学校で教わったとおり火山活動で出来た溶岩が侵食されて谷になり、そしてそのまま沈んだのだ。
なので長崎港は溺れ谷であり、リアス式海岸と呼ばれているのだ。
現在、長崎市の周辺部を取り囲む岩屋山、稲佐山、金比羅山、英彦山の山々はもともと広い台地状の大きな火山であったと言われている。約200万年前から活動を始め、約60万年前には長崎市の中心部を埋めつくすような溶岩台地が形成された。この火山は、活動が終わると侵食されて山体のほとんどを失い、残った部分が、岩屋山、稲佐山、金比羅山、英彦山の山々であると言われている。
長崎の地質
長崎火山岩類を構成する両輝石安山岩の溶岩や同質の火砕岩類(火山角礫岩、凝灰角礫岩等)でできている。
溶岩の一部は噴出後流動し、細かく砕けて火砕岩類と区別がつかない。このような溶岩を“自破砕溶岩”といい、噴火の際放出された岩片や火山灰の堆積によってできた“火砕岩類”とは成因が異なる。稲佐山登山道の途中には、火砕岩類が浸食を受け尖塔のように立っている特徴的な地形がみられる。これは通称“ローソク岩”と呼んでいるが、岩片が集まって固結した部分と凝灰岩の部分の浸食の違いによって生じたものである。
稲佐山の頂上から北西の方向を見ると、福田のゴルフ場の平坦な面が見える。これは“メサ”地形で、浸食作用の違いによって硬い溶岩の部分が残ったものである。https://www.pref.nagasaki.jp/sizen/1guidebook/nagasakiguide/naga10/naga10idx.html
教科書みたいな文章なのですんなり頭に入ってこない。
両輝石安山岩の溶岩とはまず火山岩である。
そして、その岩の中に2種類の輝石(ガラス光沢を持つ短い柱のような結晶)が入っている。もう一つは火砕岩類(火山角礫岩、凝灰角礫岩等)
火山角礫岩とは火山灰より大きな岩塊を含む凝灰岩。凝灰角礫岩とは火山灰を主体とし、火山岩塊や火山礫を含む岩石
である。
稲佐山登山道の途中には、火砕岩類が浸食を受け尖塔のように立っている特徴的な地形がみられるとある。
確かに稲佐山の中腹に真っ直ぐに立つ岩石があった。
なんとなく象に似ているので象岩とか呼んでいる岩があったり、チ○ポ岩なんて呼んでいる岩があった。通称“ローソク岩”というのは知らなかった。
そんな火山岩で出来た地形なので、奇岩や大岩が海岸にゴロゴロしているのだ。
水の浦町に巨岩が多いのもそんな理由からである。
モノレール
最後にこの町にはモノレールがある。

水の浦町のモノレール
これは長崎市の斜面移送システム整備事業で平成13年度事業化し、3グル-プの機器を実際に市内3箇所に設置している。
天神町(市道天神町1号線)
立山地区(市道勝山立山1号線)
水の浦地区(市道水の浦町大鳥町1号線)
の3箇所である。
話には聞いていたが実際設置されるのは初めて見た。
長崎の地域活性化の為にいろいろやるのは良いのだが、市民の税金で作られたものなので、今も活用されているかどうか知りたいものである。

稲佐山中腹から