「可愛い」の文化は「いとおかし」
女子高校生が、子犬を見てかわいい!と嬌声を上げる。
そして、ブルドックを見て、「ブサ可愛い!」と同じように嬌声を上げる。
はて、ブサ可愛い!とは、不細工で可愛いと言う事らしいとは察しはつくが、中年以降の人たちは、首をかしげる。
中年以降のボキャブラリーなら、ブルドックの顔は「変な顔だけど、愛嬌がある」といったところか。
「愛嬌がある」が女子高校生の「可愛い」に一番近い言葉だと考えるのだが、微妙に違うらしい。
ハローキティ、パフィー、ポケモンなど、「かわいい」といわれるものが、商品として外国にも大好評である。

ポケモン
いまや、日本のサブカルチャーは、商品として世界に大うけである。
アニメや漫画はもちろん、その売り上げはたいしたものなのだ。
「可愛い」の語源は「可哀想」である。
元の意味は不憫だとか気の毒という意味合いである。
この可哀想が、反対の愛らしいと変わったのは中世以降だと言われている。
ちなみに「可愛い」という漢字は当て字である。
今では一人歩きしている「可愛い」だが、元の意味の可哀想のニュアンスを引き継いでいるように思える。
例えば、「キモかわいい」というのは、「見た目の印象が気持ち悪いけど可愛い」という意味である。
その意味を察するとこうなる。
「気持ち悪い」ものは、可哀想であり、不憫だ。
しかし、それでも健気に生きている。
その健気なさが、好ましい
だから「可愛い」のだ。
ミィフィーというキャラクターがある。
無表情なウサギである。
これもまた、可愛いの定義に当てはまる。
表情がないのは可哀想だけど、それでも健気に生きている。
その健気なさが、好ましいので「可愛い」である。
今流行のゆるキャラも同じ公式が当てはまる。
これは、仏教で言うところの慈悲であり、憐憫の情である。
今の女子は小学生から大学生まで、この「慈悲」「憐憫の情」を表現しているのだ。
この「可愛い」文化は、携帯電話やスマホを若い女子(小学生から大学生まで)が手にした時から、始まったともいえる。

スマートフォンを操作する女性
即時性のある通信手段は、電話からメールへと「短文の文化」に火をつけた。
あの絵文字が代表選手で、感動を「カワイイ」という短い言葉で伝えようとした。
そして、以心伝心で女子の世界に広まっていった。
恐るべし「若年大和なでしこ」である。
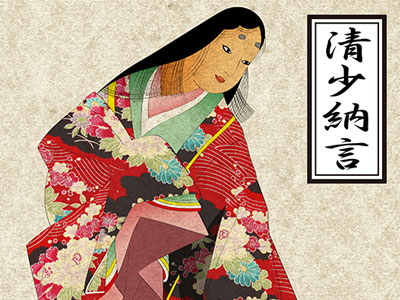
清少納言
平安時代の「枕草子」に使われている「いとおかし」という言葉には五つの意味があるという。
1 美しい、きれいな、愛らしい
2 すばらしい、優れた、見事な
3 趣がある、風情がある
4 興味深い、おもしろい
5 こっけいな、おかしい
この「いとおかし」と「可愛い」にはどこか共通点がある。
やはり、恐るべし「若年大和なでしこ」たちよ。

