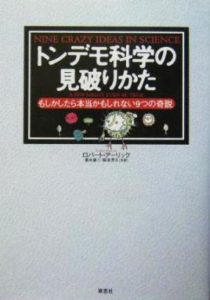日本が文字を持たなかった理由 造詣に込めた情報たち
古代日本人は、文字というものを持っていなかった。
もしかしたら、持っていたかもしれないが、記録として残っていないので、一般論として持っていなかったと仮定したい。
日本が文字、つまり漢字を取り込んだのは、聖徳太子の時代である。
仏教の経典の事もあるだろうし、唐の真似をしたというのもある。
律令という制度を持ち込んだせいもあろう。
しかし、中国大陸とは長い付き合いの倭国である。
漢字の存在も知っていただろうし、必要な場合つかってもいたと思われる。
ここまでは、皆さん異論はないと思う。
今回のタイトルである「日本が文字を持たなかった理由」について私見を述べたい。
何故文字を持たなかったのかという事について、文化が遅れていたからというのは的外れである。
倭という国が、文字というものに対して、それほど期待はしてなかったということに尽きると思う。
記号から発展した文字に、その時代あまり興味を示さなかったのだ。
漢字は、中国の夏の時代に発生したと言われている。
その時は記号と大差はなかったといわれている。
そして文字としての漢字の出現は約3300年前だと考えられる。
漢字が神との交信記録を記していた「殷」から、実用的な文字として活用され始めたのが「周」である。
紀元前10世紀から紀元前3世紀の時代で、日本は弥生時代である。
何故中国で文字の実用化が進んだかといえば、中国統一の戦乱期だったからだ。
様々な部族に連絡を取ったり、命令を伝えたりと使われている。
その為には、言葉の違う部族と意思疎通のためのアイテムが必要だった。
それが漢字である。
日本はどうかというと、平和的な縄文時代から、気候の変化という理由で稲作に手を出し始めていた時期だった。
元々島国で、大きな戦争には縁がない地域である。
文字を発達させる状況はなかったのだ。
だから、文字というものに興味を示さなかったといえる。
漢字が日本に入ってからの、その活用方法は皆さんもよく知っている。
ひらがながあり、カタカナがある。
なぜ、漢字だけでは足りなかったのか。
それは、日本人の言葉の複雑さに原因がある。
日本語は、世界一複雑な言語と呼ばれている。
ヨーロッパはアルファベットだけで事足りるし、中国は漢字だけで十分だ。
ところが、日本は漢字以外にひらがな、カタカナが必要だったのだ。
そして、漢字にも音や訓がついている。
これらの言葉を総合して、表現をしている事に注目しなければならない。
日本語の特徴として、擬音が多かったり、オノマトペと呼ばれる自然界の音・声、物事の状態や動きなどを音(おん)で象徴的に表した言葉がある。
これは音象徴語とよばれていて、擬音語・擬声語・擬態語などが含まれている。
現在の研究で日本語の特徴が研究されているが、この多様性という特徴は古代から存在していたのだ。
つまり、古代日本でも、通常の表現の中に、このオノマトペがふんだんに存在していた可能性は高い。
ガチャガチャ、キラキラ、コン、ポン、ワクワク、スベスベなどがオノマトペなのだが、古代もこれを使っていたのだ。
それ以外にも、微妙な感覚を表す言葉が多い。
「ひりひり」すると「びりびり」するといった似ているけど違う表現である。
これは単一民族だからこそ生まれてきた、感覚的な表現だといえるだろう。
複雑すぎる日本人の表現
古代日本語の話し言葉を、文字にするには複雑すぎたのだ。
万葉集というのがある。
7世紀後半から8世紀後半にかけて編まれた日本に現存する最古の和歌集である。
天皇、貴族から下級官人、防人などさまざまな身分の人間が詠んだ歌を4500首以上も集めたもので、成立は759年(天平宝字3年)以後とみられる。
日本語における文字の使用は、5世紀から6世紀頃の漢字の輸入からだといわれている。
重要なのは漢字が使われたから、和歌が出来たのではない。
すでに歌と呼ばれる形式が、日本に存在していたのを、漢字の音を使って記録したのだ。
万葉集にある枕詞だが、昔古代朝鮮語で読むと意味がわかるという本があった。
古代朝鮮語とはなんだろうか。
朝鮮半島には、様々な言葉を持った集団が住んでいて、朝鮮語という言葉で統一されていない事は事実である。
まあ、過去話題にはなったがトンデモ本である。
枕詞こそ、倭人が使っていた表現なのである。
チハヤブルとかタラチネなど古代の倭人たちは表現としていた言葉であろう。
現代では、その意味がわからないので適当な解釈を付けている。
例えばタラチネは「垂乳根乃」「足乳根乃」等の表記が多い。
一般的には、おっぱいの垂れた母親というかかり言葉といわれているが、本当は不明なのである。
もしかするとオノマトペの様に、独特の表現だった可能性のほうが高い。
古代の倭人たちは、おしゃべりだったのではないか。
コミュニケーションが豊富で、村社会。そんなイメージがある。
あの魏志倭人伝に書かれている邪馬台国の風俗の描写を読めば、その当時の様子がうかがい知れる。
「集会での振る舞いには、父子・男女の区別がない。人々は酒が好きである。敬意を示す作法は、拍手を打って、うずくまり、拝む。人は長命であり、百歳や九十、八十歳の者もいる。
女は慎み深く嫉妬しない。盗みはなく、争論も少ない。
宗族には尊卑の序列があり、上のもののいいつけはよく守られる」抜粋
穏やかな場所には、文字は必要ないのだろうか。
文字の重要性が発揮できるのは、契約書である。
実際アルファベットが出来たのも、商業の為の必要性からである。
漢字が出来たのは、戦時の伝令系統の記録としてである。
宗教のユダヤ教の十戒もその一つだと言える。
倭国には、そんな契約が存在しなかった。
神道には経典はない。
経典はなくても、信仰には何の不自由はない。
伝えたいものは形で表す。
縄文時代の土偶を見れば、その表現のすばらしさはひときわ目立つ。
その土偶を見れば、意味が通じたのだ。
埴輪もそうである。
家を表現するのに文字を使えば、多大な労力を費やし、それでも伝えきれないだろう。
形こそが情報の集大成なのだ。
話し言葉が複雑で、平穏な時代という好条件が重なれば、文字より造詣が発達する。
そんな仮説が成り立つ。
縄文のメドゥーサ 田中 基(著)で紹介されている、釣手土器の不思議な造詣に、田中氏は古事記の神話の物語が込められていると書いている。

釣手土器
それ以外にも、数々の独特の造詣を持つ土器はよく知られている。

札沢遺跡 動物装飾付釣手土器
これらは、物語を込めて作られていると推測される。
作られた像を見て話す事で、記憶は確実に受け継がれている。
まさに、マルチメディアの発想である。
文字の記録性の不完全さを知り、造詣に進んだと思われる。
世界にも文字を持たなかった国がある。
それらの地域にも、物語を込められた像が多く作られているのがわかる。
インカ帝国のマスク

シカン黄金大仮面
三星堆遺跡

青銅縦目仮面
弥生時代の埴輪

埴輪
前方後円墳

世界最大の前方後円墳
文字ではなく造詣に進んだ国々は、豊かな精神世界を持っていたのだ。
しかし、文字を持った国々は、軍事と経済を発達させ地球上の覇権を握ったのは現実である。
日本の場合、島国だったという幸運と、日本人の危機感と多様性により、文字の文化に突入した。
そして、その文字は中国の漢字を導入したのだが、ひらがな、カタカナなどを付け加え、豊かな造詣の文化に加え、文字を活用し始めたのである。
日本が文字を持たなかった理由は、情報量が多すぎて、伝達手段に文字よりも造詣を選んだというのが結論である。
そして、文字を使う事になったが、その情報が多すぎて漢字をベースに2つの表音文字を作って、情報不足を補っている。
現代、メールなのでよく使われている絵文字だが、これも日本発生である。
q(*^O^*)p v(*^o^*)v
日本の漫画は世界中で読まれているが、漫画で使われている擬音の進化がすごい。

ジョジョの奇妙な冒険
その感覚的な表現が、世界に受け入れられていると評論家は解説している。
これからの日本人が、どんな多彩の表現を使うのか興味津々である。