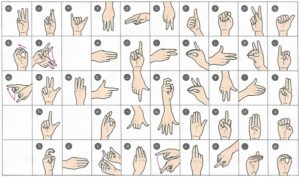諫早と宇佐神宮との謎のつながり
御館山稲荷神社のフリー写真素材
http://freephoto.artworks-inter.net/mitachiyama/kaisetu.html御館山(みたちやま)は、一千三百余年昔の大宝年間(西暦七〇一~七〇三年)に、行基菩薩が九州巡行の折、五智光山として開基されました。平安末期、鎮西八郎為朝が館を築き武術を練ったことから、御館山と呼ばれるようになったと伝えられています。

御館山稲荷神社
今年の初詣は、諫早にある御館山(みたちやま)稲荷神社に参ることになった。
境内は、佐賀の祐徳稲荷のようで、聞いてみると新しく作ったらしい。
社殿は見た目も新しく、近くに専用駐車場もたくさんあるので諫早の人たちも数多く訪れているらしい。
御館山(みたちやま)のいう名称は、平安末期、鎮西八郎為朝が館を築き武術を練ったことからきているらしい。
鎮西八郎為朝伝説
鎮西八郎為朝伝説は九州にも多くある。
源 為朝(みなもと の ためとも)は、平安時代末期の武将。源為義の八男。源頼朝、義経兄弟の叔父にあたる。
身長2mを超える巨体のうえ気性が荒く、また剛弓の使い手で剛勇無双を謳われた。
生まれつき乱暴者で父の為義に持てあまされ、僻地の九州に追放されたが手下を集めて暴れまわり、一帯を制覇して鎮西八郎を名乗る。ウィキペディア
佐賀県の黒髪山に為朝が角が7本ある大蛇を退治したという伝説が残っている。
琉球王国の正史『中山世鑑』や『おもろさうし』、『鎮西琉球記』、『椿説弓張月』などでは、このとき源為朝が琉球へ逃れ、その子が初代琉球王舜天になったとしている。
曲亭馬琴の『椿説弓張月』という小説があるくらい有名な武将だ。

椿説弓張月
長崎の矢上というところにも、鎮西八郎為朝伝説の伝説があり、矢上に流れる川は、ずばり「八郎川」という。
鎮西八郎為朝の矢受け石(天狗岩)というのもあり、為朝が御館山の頂上から弓を射、その矢は小豆崎にまで届いたそうで「矢着崎」がなまって「小豆崎」になったと伝えられている。
このパターンは、矢上の地名の由来と同じパターンだ。
御館山(みたちやま)は、大宝年間(西暦七〇一~七〇三年)に、行基が九州巡行の折、五智光山として開基したとある。
行基は奈良時代の僧で、各地で社会事業を行っていた。
長崎県内にも、行基が開いたとされる寺はたくさんある。
行基が実際に訪れてはいないと思うが、大僧正にまでなったえらいお坊さんなので、各地の伝説として名前が使われたのだろう。
年代も伝説なのではっきり出来ないが、巨石が信仰の対象になっているので、かなり古代より山は開かれていたのだろう。

御館山稲荷神社
天狗の伝説があるので、山伏信仰の場所だったと思われる。
諫早市のど真ん中にある、天狗を祭った御館山稲荷神社。
なにか謎があるような気がする。
不思議な諫早
平安時代の諫早は、歴史書にのっていないが、大分県宇佐神宮に保管されている建久8年(1197年)の『八幡宇佐神宮神領大鏡』という文書の中に、「伊佐早村」が初めて登場する。
なぜ大分県宇佐神宮の記録に、長崎の諫早があるのが謎である。
さらに、伊佐早村の本領主が、もともと公領であったこの地方を、平安時代の末期には宇佐神宮の荘園として寄進していたことが書かれている。

大分県宇佐神宮
宇佐神宮は八幡様の総本宮であり、参拝作法の四拍手が有名である。
また、八幡様の語源になったといわれる、渡来人集団秦氏の本拠地でもある。
秦氏は古代大和国を作り上げるための、大きな勢力となっており、さまざまな伝説が秦氏から生まれている。
そんな宇佐神宮の荘園になるくらいなので、諫早と秦氏は関係があると見ていいと思う。
一説には、実力派の宇佐神宮の荘園になることで、諫早の安全を図るため寄進したとも言われているが、何せ場所が遠い。
無名の諫早が、宇佐神宮の荘園になったくらいでは、不穏な時代での安全を確保したとはいえないと思う。
宇佐大鏡の注記では、諫早の領主は、染貫主(そめのかんじゅ)であったとある。
染貫主は、宇佐宮にかかわり染色関係の仕事をする職人集団の長である。
秦氏は、渡来系の技術者集団でもある。
彼らは、無名の諫早に常駐していたのである。
そんなにこの諫早というのは重要だったのであろうか。
諫早には、古代史に記録を残すようなものは何もないはずだ。
諫早というより、長崎は古代史からそぎ落とされたような感じさえ受ける。
しかし、もっと古い時代の記録には島原の国津神のことがのっている。
景行天皇九州巡である。
肥前風土記「僕者此の山の神、名は高来津座、天皇の使の来るを聞き迎え奉る而巳」因って高来の郡と曰ふ。筑紫国魂神社記に是国魂の神、高来津坐神作り而現耳。
つまり、島原に「高来津坐神」という地方の豪族がいて、大和に従ったとされている。
この伝説がある高来郡は諫早の隣にある。
なんだかとっても匂うのだ。
諫早の古代
宇佐神宮の荘園になった諫早は無名ではないのだ。
諫早一帯は古代の高来津坐神がおさめる地域だった。
そして、島原市に行く途中に守山大塚(もりやまおおつか)古墳という前方後円墳がある。

守山大塚(もりやまおおつか)古墳
大村彼杵の荘にはひさご塚古墳という前方後円墳がある。

ひさご塚古墳
時代はばらつくが、間違いなく前方後円墳である。
そして、その古墳を作った集団の記録はない。
もしかしたら、古墳を作った集団は、秦氏一族の可能性もある。
そうなると、諫早と宇佐神宮が初めてつながるのだ。
四面上宮と船魂明神
御館山(みたちやま)にある四面上宮と船魂明神。
四面宮は雲仙の温泉神社、国見町神代にもある。
四面の由来は国生みの神話に出てくる筑紫島からきている。
『古事記』の「次に、筑紫の島を生む、子の島もまた、身一つにして面が四つあり、面ごとに名がある」から四面神はきている。
さらに四面神の分身末社として山田神、有家神、千々石神、伊佐早神が祭られている。
船魂明神(ふなだまみょうじん)は、夜光る霊光が有明海の漁夫の大漁を守ったという言い伝えがある。
こんな伝説は長崎にもたくさんある。
海を舞台に活躍する集団が御館山(みたちやま)にいた証拠ではないかと思う。
現在の諫早はかなり埋め立てられていて、古代は諫早の中心部まで海がきていたといわれている。
その証拠に、いろんな所に恵比寿様が祭られている。
さらに言うならば、宮崎康平氏の「まぼろしの邪馬台国」では、諫早と島原の間くらいに、邪馬台国があったと述べている。
これらのことを考えると、あの秦一族が諫早に居坐っていたのも理解できるのだ。
ここまで書いても「トンでも説」としてかたずけられそうだ。
山城のような御館山(みたちやま)にも秦氏の守り神である稲荷神社がある。
宇佐神社の荘園だった諫早である。
なぜ諫早の領主が歴代、宇佐神社の染貫主(そめのかんじゅ)だったのか。
その謎を解くのは宇佐神社と秦一族だけなのである。

御館山稲荷神社