長崎の原風景(3) 野母崎の葛城の神と土蜘蛛
丹治比一族が長崎にいたことは事実である。
彼らは何を生業としていたのだろうか。そもそも、丹治比一族とはどんな集団であろうか。
丹治氏は古くからの名族で元をたどれば皇族にたどり着く。
現在の福島市に沢山ある姓である。丹治、丹治比などさまざまな変化があるが、大本は丹生(にゅう)つまり水銀にかかわっていたのは間違いないようだ。
純粋な武士と呼ばれている人たちの確立は、かなり昔に遡る。平清盛は武家集団国家を実現させた。

平清盛
1100年代のことである。
1159年平清盛が42歳の時、「平治の乱」が起こる。その時源義朝と戦い、勝利して武士のトップに立つ。
もちろん、中心は天皇を頂点とする貴族だが、実質の支配を武士が初めて行ったという意味である。
その後、源氏が平家を破り、鎌倉幕府を開く。
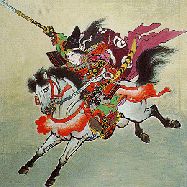
源頼朝
武士とは、朝廷や国衙から職業的な戦士身分と認められた人びと』のことであり、武装しているからといって『武士』ではない。
公的に武装を認められて初めて『武士』なのである。
これは、拳銃を持っているからといって、ヤクザは警官ではないのと同じだ。 発展 『武士の発生』 http://www.geocities.jp/michio_nozawa/10hatten/hatten7.html
つまり武士というのは、国家権力が出来上がって、そこからの指名があって初めて「武士」が誕生するという仕組みである。
平家の支配から源氏の支配になったのだが、全日本がすべて源氏になったわけではない。
特に九州はそれ以降も平家の支配圏の名残がある地域だった。
源氏は柔軟な対応をして地元の豪族の支配権をある程度認める。
このあたりからは、記録が残っているので確実である。
御家人となった長崎の豪族達は、その役目として京都に行き、貴族の警護を務めている。
その時の記録に、長崎氏や時津氏、戸町氏は「丹治比」を本姓としている。
僕が知りたいのは「丹治比一族」までの長崎なのである。
古代の話しには壱岐対馬がメインで出てくる。平戸や五島もかなり出てくる。
しかし一番知りたいのは大陸との関係である。
4世紀ころに大和王権は確立されたという。この時期に日本国というのが形作られた。
その頃の話しに「土蜘蛛」という名の土豪集団がいた。
これは長崎だけの話しではない。
九州全域の話しである。 「土蜘蛛」とは、上古に天皇に恭順しなかった土豪たちであるという。
特に有名にのが葛城山の土蜘蛛である。
葛城山の土蜘蛛 - Google 検索
土蜘蛛の中でも、奈良県の大和葛城山にいたというものは特に知られている。
大和葛城山の葛城一言主神社には土蜘蛛塚という小さな塚があるが、これは神武天皇が土蜘蛛を捕え、彼らの怨念が復活しないように頭、胴、足と別々に埋めた跡といわれる[5](神武天皇も参照)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E8%9C%98%E8%9B%9B
野母崎
長崎半島の先端に野母崎という地域がある。その野母崎にこんな話が残っている。
7世紀半ば紀州熊野の漁師夫婦が野母に漂流した。
命が助かったのは熊野さんのおかげだと、山の上に祠をたてて住み着いたが夫の方は熊野へ帰ってしまった。
また、野母崎の地名は「野の母が開いた」というので野母崎となった。
また長崎市野母町の伝統行事には約1300年の歴史があるとされ、1972年に国の無形民俗文化財に指定されている。
約1300年前というと、西暦700年ということになる。
西暦700年前後は飛鳥時代、奈良時代である。
646年(大化2年) - 改新の詔を宣する。(大化の改新)
663年(天智天皇2年) - 白村江の戦い(はくすきのえのたたかい)で大敗する。
670年(天智天皇9年) - 全国的に戸籍を作る(庚午年籍)。
701年(大宝元年) - 大宝律令の撰定完成する。
710年(和銅3年) - 平城京に遷都する。
大化の改新で、日本は大きく変わっていくが、白村江の戦いでひどい負け方も経験している。
激動の時代である。
その野母崎には浦祭りというのがある。
奉納踊りは「鉾舞(ほこまい)」「モッセー」「中老(ちゅうろう)」「トノギャン」で構成されている。
![0[1]](http://artworks-inter.net/ebook/wp-content/uploads/01-e1419724797815-300x164.jpg)
野母浦まつり - Google 検索 2013.8.13
野母浦祭 『ちゅうろう』
「中老」の催馬楽(さいばら)の歌 「催馬楽」は鎌倉時代から伝わる宮廷歌謡の一つ。
その中の代表的な歌が「ちゅうろう(中老)」で、「文書き」など18種類があります。
「催馬楽」はもともと一般庶民のあいだで歌われていた歌謡で、決められた歌詞や音律はない。
野母崎の「ちゅうろう」の中に「契ぞうすき」という文言がある。葛城の神と契りを結んでいるという内容である。
かつらぎ(葛城)というのは 奈良県盆地の古地名である。
葛城の神 - Google 検索
葛城氏は、大王(のちの「天皇」)家確立後、葛城「臣」となるが、かつては大王家に対抗できる最大の豪族、あるいはもう一つの「大王家」であった。
かつらぎの神というと、大和の国(奈良県)葛城山に住むという一言主神(ひとことぬしのかみ)である。一言主神(ひとことぬしのかみ)は「吾は悪事も一言、善事も一言、言い離つ神。葛城の一言主の大神なり」と言ったとある。
これは、大和国の天皇族と対抗していた、もう一つの大王族の存在を明確に示す。 以上の内容を整理する。
1.7世紀半ば紀州熊野の漁師夫婦が野母に漂流して住み着いた。
2.現在も続いている野母崎の祭に葛城の神と契りを結んでいるという歌詞がある。
3.肥前の国には上古に天皇に恭順しなかった土豪たち「土蜘蛛」がいた。 特に有名にのが葛城山の土蜘蛛である。
上記の事から推測すれば、野母崎には葛城氏に関係ある人々が住んでいたことになる。
しかし長崎の古文書を読んでも、そんな記録は何処にもない。
そもそも、野母崎に宮廷歌謡が有ること自体不思議なのだ。
役小角
野母崎の樺島に行者山という山がある。
行者とは役小角(えん の おづの)の事をいう。役行者は、鬼神を使役できるほどの法力を持っていた。
後に島流しにされるが、葛城の神は役小角の法力によって子分扱いになっていた。
この西の果ての長崎の更に西にある野母崎半島に行者山がある。
野母漁港近くの丘に熊野神社(本拠地は紀伊の国)がある。
東長崎の鶴の尾付近には役行者(えんのぎょうしゃ)神社がある。
野母崎には鎌倉時代から伝わる宮廷歌謡が存在する。
さらに長崎半島には宮摺という地域がある。町名の由来は宮修理から来ているという。(長崎市内に宮廷関係の遺跡はない)
どうだろうか。
長崎に住み着いた反大和の葛城一族
熊野に大和大王と拮抗した一族が有り、その一族の大部分は大和王権に取り込まれていった。
しかし、反大和のグループは自分たちの国を目指し、南に旅立った。
その一族がたどり着いた場所が野母崎だ。
何故野母崎かというと、大陸に一番近いからである。
そして、土蜘蛛と呼ばれている反大和の集団が大勢いたからである。
葛城の神と土蜘蛛、そして「丹治比一族」
長崎の原風景の一場面が見えてきた。
![d82696[1]](http://artworks-inter.net/ebook/wp-content/uploads/d826961-300x200.jpg)
![koumura[1]](http://artworks-inter.net/ebook/wp-content/uploads/koumura1-300x200.jpg)
![d0128163_17131715[1]](http://artworks-inter.net/ebook/wp-content/uploads/d0128163_171317151-300x282.jpg)
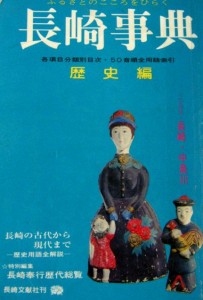
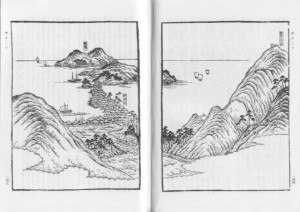
“長崎の原風景(3) 野母崎の葛城の神と土蜘蛛” に対して1件のコメントがあります。